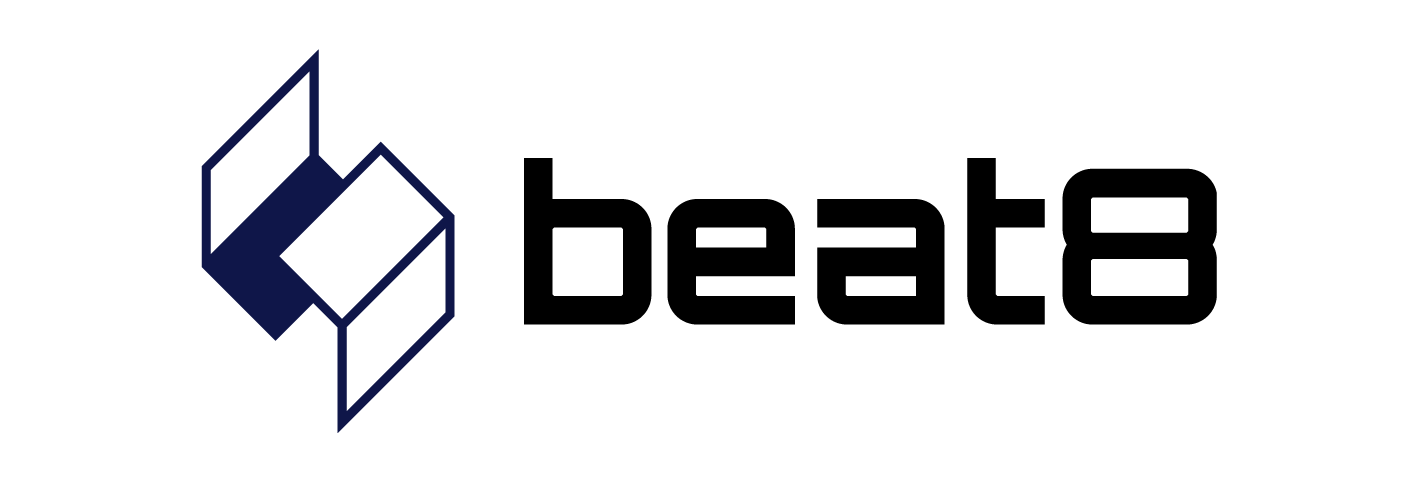相続したマンションの活用方法
相続したマンションをどうするかは、相続人の状況や希望、マンションの状態や市場環境によって異なります。
しかし、一般的にマンションを相続したら「住んで保有し続ける」か「賃貸に出す」か「売却する」かのいずれかの方法で活用されることになります。
相続したマンションの活用方法のメリット・デメリットをまとめました。
| 活用方法 | メリット | デメリット |
| 住んで保有し続ける | 時間を欠けて利用計画が立てられる手続きや税金、費用負担がない | 保有するコストがかかり続ける定期的なメンテナンスが必要 |
| 賃貸に出す | 安定した家賃収入タイミングが良い時に売却するという選択肢が残る | 管理に手間とコストがかかる空室になるリスクがある十分な収入が得られない |
| 売却する | 現金化が可能になる経済的負担から開放される価値が下がるリスクを回避 | 期待する売却益が得られない心理的な負担を感じる |
マンションをそのまま保有するメリットとデメリット
マンションをそのまま保有するメリット1つ目は、保有することで、将来の利用計画が決まるまで時間を確保できる点です
例えば、将来の住居として利用する場合や、家族のために保有しておく場合などがあります。
2つ目に売却や賃貸に出すことで発生する手続きや税金、費用を今すぐに負担する必要がない点です。
反対にデメリットは、固定資産税や管理費など、マンションを保有するコストがかかり続ける点です。これが長期的に負担になる可能性があります。
また、市場環境が悪化し、マンションの価値が下がるリスクがあります。
そのため、考慮すべき点として将来的な活用計画がない場合、長期間保有することでかかるコストとリスクをしっかりと把握することが重要です。
加えて、マンションの状態が悪化しないよう、定期的なメンテナンスを行う必要があります。
マンションを賃貸に出すメリットとデメリット
マンションを賃貸に出すメリットは、賃貸に出すことで、安定した家賃収入を得ることができる点です。これは、長期的な資産運用として有効です。
また、マンションを保有し続けることで、将来的に価値が上がった場合に再度売却するという選択肢も残されます。
一方でデメリットとして、賃貸管理には、手間とコストがかかります。例えば、入居者の募集、契約管理、メンテナンスなどが必要な点も覚えておきましょう。
また、空室期間が発生するリスクや、入居者トラブルのリスクも考慮しなければなりませんし、マンションの築年数が古い場合、賃貸に出しても十分な収益が得られない可能性もあります。
そのため考慮すべきこととして、抑えておきたいのが賃貸管理を専門の管理会社に委託することで、手間を軽減することができますが、その分手数料が発生する点です。
また、物件が賃貸市場においてどれくらいの需要があるかを調査し、収支の見通しを立てることが重要です。
マンションを売却するメリットとデメリット
最後にマンションを売却するメリットとデメリットを紹介します。
メリットの1つ目は、相続したマンションを売却することで、現金化が可能になり、相続税や他の相続関連費用の支払いに充てることができます。
また、売却によって、マンションの維持費や管理費、固定資産税などの経済的負担から解放される点も大きいメリットです。
さらにマンションが古く、将来的に価値が下がる可能性がある場合、早期に売却することでリスクを回避できます。
一方で、デメリットを紹介すると、市場価格が思ったほど高くない場合、期待する売却益が得られない可能性があります。また、マンションが思い出の詰まった場所である場合、売却することに心理的な負担を感じるかもしれません。
そこで考慮すべきこととして、マンションの市場価値を正確に把握するために、不動産会社に査定を依頼することが重要です。また、売却に伴う譲渡所得税やその他の費用について、税理士に相談することをお勧めします。
マンションを相続して売却する時の流れ
相続したマンションを売却する手続きは、一般的なマンション売却の方法と異なります。
ここからは、相続したマンションを売却する場合の一連の流れを紹介します。
- マンションの所有者の死亡
- 相続人調査
- 遺産分割協議
- マンションの名義変更
- 確定申告・相続税の支払い
- マンション売却の準備
- 不動産会社への査定依頼
- 不動産会社選び・媒介契約締結
- 売却活動
- 買い手と売買契約締結
- 引渡し・入金
- 確定申告
ここからは、マンションの所有者が亡くなった後の流れを詳しく見ていきましょう。
相続人調査・相続財産調査
身近な方が亡くなったら、相続手続きが行われます。まずはじめに行うのが、相続人の人数と相続すべき財産の全体像を把握するための「相続人調査」と「相続財産調査」です。
民法という法律では、故人の財産を相続できる人(=法定相続人)の範囲と優先順位が定められています。そこで、故人やその家族の戸籍を遡ることにより、法律に従って法定相続人を確定させる必要があります。同時に、借金などマイナスの財産を含めた相続財産がどれくらいあるかも調査しなければなりません。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によってどのように故人の財産を分割するかを話し合います。この遺産分割協議は、必ず相続権を持つすべての人で行わなければならず、協議のあとからほかに相続人がいることが判明した場合、すでに合意を得られている場合も、その協議は無効となってしまいます。相続財産に関しても同様で、遺産分割協議のあとに新たな財産が見つかった場合、その規模によっては、協議が無効となってしまう可能性があります。
そのため、相続人調査、相続財産調査は、遺産分割協議の前に完了させておく必要があるのです。
遺産分割協議
法定相続人が複数いる場合は、話し合いによってどのように遺産を分けていくかを決めなければなりません。故人が遺言を残している場合、基本的には遺言書に記載の内容に従って遺産を分割します。しかし、遺産分割協議ですべての相続人の同意が得られれば、遺言書に従わない遺産分割も可能です。
不動産がある場合の遺産分割は複雑
現金や預貯金などは「誰にいくら」と法定相続分に従って分けることができますが、土地や建物などの不動産は、半分、1/3ずつ、などと分割するわけにはいきません。そのため、相続財産に不動産が含まれる場合の遺産分割は、少々複雑です。
遺産分割の方法には、主に以下の4つがあります。
【 現物分割 】
土地と建物は妻に、預貯金は長男に、株式などの有価証券は長女に、といったように、現物をそのまま、1人の相続人が相続する方法です。場合によっては公平性に欠ける可能性もありますが、不動産がある場合にはもっともわかりやすい遺産分割の方法となります。
【 代償分割 】
1人の相続人が土地や建物を相続した場合に、不動産を相続した人がほかの相続人へ、それぞれの相続分を現金などで補てんする遺産分割方法です。現物分割に比べて公平性はあるものの、不動産を相続する人に支払い能力があることが前提となります。
【 換価分割 】
不動産など分けられない遺産は売却して換金し、売却益と預貯金などそのほかの遺産と合わせて、それぞれの相続分に従って分配する方法です。この場合、遺産分割協議書に換価分割であることを明記するようにしましょう。
【 共有分割 】
不動産などの分けられない遺産がある場合、相続人同士が共同で所有権を持ちます。故人の遺産をそのままの形で残した上で公平性を担保することが可能な遺産分割方法ではありますが、持分に従った利益の配分が複雑であったり、将来的に売却したくなっても、1人の所有者の独断では処分できなかったりするデメリットがあります。
相続財産にマンションなどの不動産が含まれる場合、共有分割の方法を選択すると、一見平等に思えるものの、あとからトラブルになる可能性が高くなります。そのため、住む人がいない物件の場合は換価分割、遺産を不動産として残しておきたい、誰かが住まいとして引き続き住み続ける、といった場合は、現物分割や代償分割の方法をとるのがよいといえます。
ローン残債がある場合における不動産の遺産分割の考え方
相続する不動産にローンが残っている場合、換価分割ならば、売却益からローン残債と諸経費を差し引き、残った利益を分割します。そのほかの遺産分割の場合は、不動産を相続した人が同時にローンの残債も相続します。
とはいえ、住宅ローンを組む際は、ほとんどの方が団体信用生命保険(通称“団信”。住宅ローンの契約者が死亡などの理由により、ローンが払えなくなった場合、ローン残債の支払いが免除される生命保険)に加入します。そのため、故人が亡くなられたときには、住宅ローンも完済しているケースがほとんどです。
マンションの名義変更(相続登記)
遺産分割協議において不動産を相続する人が決まったら、相続人は不動産の名義を故人から自分に移す手続きをしなくてはなりません。この手続きは、相続登記や所有権移転登記と呼ばれます。2024年4月1日より、相続登記の法律が改正されました。
3年以内の相続登記が義務化され、正当な理由なく義務に違反したものは、10万円以下の罰金がペナルティとして課せられます。
これまで登記の期限がなかったため、法改正を認識していない方は注意が必要です。期間ギリギリで焦って申請するとトラブルに繋がる可能性が高くなります。マンションを相続したら、尾羽やmに登記申請を行うようにしましょう。
不動産を売却したりローンの担保にしたりしたい場合、名義を変更していないと手続きを進められません。そのため、相続が確定した時点で相続登記を行うのが一般的です。
相続登記には、相続した不動産の所在地を管轄する法務局へ、必要書類の提出と免許登録税の納付が必要です。免許登録税は、相続した不動産の固定資産評価額×0.4%。固定資産評価額は、法務局より毎年送付される固定資産税の課税明細に記載されています。または、市区町村役場にて固定資産評価額証明書を取得することでも確認できます。
確定申告・相続税支払い
相続によって不動産を取得した場合、確定申告や相続税の納付が必要なケースがあります。相続税の申告や支払いには期限もあり、不明なまま手続きを怠っていると、後々課税のペナルティを受ける可能性も否めません。
ただし、取得した不動産の価値が基礎控除額内に収まる場合、相続税を支払う必要はありません。相続税に関する手続きは複雑なため、司法書士や税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。
マンションの売却を少しでも検討しているのであれば、「自分のマンションがいくらで売却出来そうか」を把握しておきましょう。
そのためには、不動産会社から査定を受ける必要があります。弊社では、売却査定を無料で承っております。まずはお気軽にご相談ください。
相続したマンションの売却時にかかる税金
相続したマンションを売却する際には、主に以下の3種類の税金が関わってきます。
印紙税
売買契約書などの重要な書類に貼付する必要がある税金です。
契約書に記載された金額によって印紙税の額が決まります。
印紙税は基本的に郵便局で購入可能ですが、額が大きくなった場合は、法務局にて購入するのが確実でしょう。
例えば、売却価格が1,000万円以上5,000万円以下の場合、印紙税は20,000円です。
2024年4月より法改正により印紙税の軽減措置が廃止されているので、注意してください。
2. 譲渡所得税等
マンション売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。
譲渡所得は「売却価格 – 取得費 – 譲渡費用」で計算されます。税率は、所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合は約40%、5年超の長期譲渡所得の場合は約20%(所得税+復興特別所得税+住民税)となります。
ただし複雑な計算が必要となりますので、具体的な金額を把握するには、税理士に相談することをおすすめします。
3. 登録免許税
不動産を売買した際に、新しい所有者の名義変更を行うために必要な税金です。
不動産1つにつき、一律1000円の費用がかかります。
マンションの売却時に、部屋と土地の両方の売却が必要な場合は、不動産2つ分が徴収される形となるため、部屋の分の【1000円】と土地の分の【1000円】、合計2000円の費用がかかります。
マンションの売却で土地まで考慮するケースは少ないのですが、売却するものが家の場合は売却対象に何が含まれるのか確認する必要があります。
マンションの相続税の計算方法
相続によりマンションを取得した場合の相続税は、以下の計算式により算出します。
(マンションの評価額[=資産価値]×税率)―控除額
また、税率と控除額は、マンションの評価額に応じて以下のように定められています。
| マンションの評価額 | 税率(控除額) |
|---|---|
| ~1,000万円以下 | 10%(なし) |
| ~3,000万円以下 | 15%(50万円) |
| ~5,000万円以下 | 20%(200万円) |
| ~1億円以下 | 30%(700万円) |
| ~2億円以下 | 40%(1,700万円) |
| ~3億円以下 | 45%(2,700万円) |
| ~6億円以下 | 50%(4,200万円) |
| 6億円~ | 55%(7,200万円) |
マンションの評価額の算出方法
マンションの評価額は、建物部分と土地部分とに分けて算出します。
土地部分の評価額
土地部分の評価額は、国税庁の定める路線価を活用し、以下の計算式で算出できます。
土地部分の評価額=路線価×マンション全体の面積×持分割合
路線価とは、簡単にいえば“公道につけられた価格”のことです。本来ならば土地は時価で算出するものですが、全国のすべての土地それぞれで相続時の時価を割り出すのは大変煩雑な作業になり、時間も要します。そこで、所有するマンションに隣接する公道の価格に、マンションが建っている土地の面積を掛けることで、土地の評価額とする「路線価方式」が採用されています。
マンションが建っている場所の路線価は、
国税庁のHP 財産評価基準
から確認することが可能です。また、持分割合は、登記簿謄本やマンション契約時の売買契約書などを見れば確認できます。
路線価がつけられていない土地の場合は?
郊外に建てられたマンションなど地価に大きな差がないところでは、路線価がつけられていないケースもあります。その場合は、路線価方式ではなく「倍率方式」で計算します。計算式は、以下のようになります。
土地の固定資産税評価額×倍率
倍率は、国税庁ではなく市区町村役場で確認してください。
建物部分の評価額
相続登記の際に調べた固定資産税評価額が、そのまま建物部分の評価額となります。つまり、土地部分と建物部分の評価額を合わせた金額が、相続したマンションの評価額となります。
マンションの評価額<基礎控除額であれば、相続税はかからない
土地と建物を合わせたマンションの評価額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税の課税対象にはなりません。基礎控除は、以下の計算式により算出されます。
(3,000万円+600万円)×法定相続人数
法定相続人が妻と子ども2人だった場合、基礎控除額は3,600万円×2=7,200万円となり、マンションの評価額が7,200万円を下回れば、相続税を支払う必要はありません。
マンションなど故人の財産を相続する場合は、基礎控除のほか、条件に当てはまればさまざまな控除を受けることが可能です。マンションなど不動産を相続する際の代表的な控除には、たとえば以下のようなものがあります。
配偶者控除
相続においては、配偶者という立場は手厚く保護されています。そのため、相続税も大幅な軽減措置を受けることが可能です。ただし、配偶者控除を受けるためには、必ず確定申告を行わなければなりません。また、申告期限までに遺産分割協議を終え、相続財産を確定させておく必要があります。
配偶者控除の控除額は1億6,000万円。つまり、故人の配偶者はきちんと手続きさえ行えば、ほとんどのケースで相続税の課税対象とはならないのです。
小規模宅地等の特例
相続したマンションが故人の宅地、つまり住まいとして利用されていた場合、故人と同居の親族が相続人であるときに受けられる控除です。宅地の建っている土地面積が330平米以下の部分に対して、相続した土地の評価額の80%が控除されます。相続したマンションが事業用として使われていた場合は、土地面積が400平米以下の部分まで80%の控除を受けられます。また、賃貸物件を相続した場合は、200平米以下の土地に対しては、50%の控除が適用されます。
相続人が故人と同居していなかった場合でも、故人と同一生計であれば、小規模宅地等の特例の対象となります。なお、相続税の申告と納税には、故人が亡くなった日の翌日から10カ月以内の期限があります。どのような控除を受けられるか、相続税の課税対象となるかどうかがわからない場合は、早めに税理士などへ相談してみましょう。
相続したマンションは売却?賃貸?
マンションなどの不動産は相続したら終わりではなく、その後にどう維持管理をしていくのか、あるいは処分するのかを決めなければなりません。住まいとして住み続けるのであれば特に問題はありませんが、維持管理費、修繕費の積立金、固定資産税とさまざまな費用がかかってくるため、ただ資産として所有し放置しておくのはおすすめできません。
マンションを相続したときの対策としては、主に
- 住み続ける
- 賃貸として貸し出す
- 売却する
の3つの選択肢があります。ここでは、賃貸と売却のメリット・デメリットを比較してみましょう。
必ずしも賃貸=安定収入とは限らない
マンションを賃貸物件として貸し出す最大のメリットは、一定の不労所得を得られることでしょう。しかし、賃貸で利益を得るには、それなりにリスクもあります。
賃貸のメリット
・家賃として安定収入が得られる
毎月、何もしなくても一定のお金を家賃収入として得られる点が、賃貸の大きなメリットのひとつです。
・資産を残せる
次の世代に相続することのできる資産が残ることも、賃貸の大きなメリットのひとつ。「いずれは地元に戻りたい」「子どもが大きくなったらマイホームを子どもに譲り、相続したマンションで老後を送りたい」などの将来像を描いているなら、定期借家契約(あらかじめ賃貸契約の期間を定めておくことで、期間満了にともない自動的に契約が終了する賃貸の形態)という選択肢もあります。
賃貸のデメリット
・諸経費や税金がかかる
“何もしなくても”一定の収入があると先述しましたが、厳密にいうとこれは正確ではありません。
まず、賃貸物件として人に貸すためには、ハウスクリーニングや、場合によってはリフォームが必要なケースもあります。また、人に貸すとなると不動産会社に仲介を依頼することになるため、不動産会社へ一定の費用を支払わなければなりません。さらに、入居後も、所有者としてマンションを維持・管理していくための費用が必要です。
加えて、一定の収益があるわけですから、税金の支払いも発生します。賃貸マンションの場合、固定資産税や維持管理費、修繕費積立金などは経費として計上できるため、所得税を減額することは可能です。しかし、しっかりとした運用知識がなければ、順調に利益を出していくことは難しいかもしれません。
・空室のリスクを考慮する必要がある
家賃として一定の収入が入るのは、あくまでも住み続けてくれる人がいる場合です。退去後にすぐに次の入居者が見つからないなど、空室の期間が長ければ利益を得られないばかりか、維持管理費を考慮すると、赤字になる可能性もあります。マンションを賃貸物件にしたい場合は、立地や周辺環境など、さまざまな条件から借り手がつくかの判断も重要なのです。
固定資産評価額=売却額ではないことに注意!
マンションを一度賃貸物件にしてしまうと、マンション経営がうまくいかないからといってあとから売却しようとしても、収益物件、経年劣化による価値の下落から、高く売れない可能性があります。そのため、どうせ売却するのであれば、できるだけ早いほうがいいという考え方もあります。
とはいえ、固定資産としての評価額がそのままマンションの売れる価格ではないこともあり、希望価格では売却できないリスクも考慮しなければなりません。
売却のメリット
・換金できる
売却益として現金が手元に残ります。
・維持管理の費用や手間がかからない
不動産を所有していると、どうしても手間やコストがかかるため、相続したマンションが現在の住まいから離れたところにあるケースなどでは特に、適切な維持管理が難しくなる可能性があります。
売却のデメリット
・資産を残せない
売却益としてまとまったお金が入る代わりに、資産としての不動産を手元に残せないデメリットがあります。
・譲渡所得税や住民税がかかる
賃貸の場合と同様、マンションの売却益には、売却時にかかった諸経費と減価償却を引いた部分に対して譲渡所得税と住民税がかかります。しかし、譲渡所得税や住民税に関しては控除も受けられるため、適切な不動産会社に任せれば、大きな負担を避けられるといえるでしょう。
相続したマンションを貸すか売るか迷ったときに考えたい2つのポイント
マンションを賃貸物件にすべきか売却すべきか迷ったら、まずは以下2つのポイントを慎重に検討してみましょう。
ライフプランをチェック
賃貸にするか売却するかの判断基準のひとつとなるのが、将来的に相続したマンションに住む可能性があるかどうかです。自身が住むのではなくても、自身の子どもや親族が住む可能性があるのであれば、資産として残しておくことを考えなければなりません。その上で、将来的に住むようになるまでの期間、賃貸物件としてどのように収益を上げていくかが重要になります。
一方で、将来的に住む可能性がない場合は、しっかりと管理・運用していかなければ不動産として抱えていても時が経てばたつほど資産価値は減っていきます。資産価値がもっとも高い段階で売却すべきという判断もできます。
借り手・売り手のニーズをチェック
マンションを貸すにしても売るにしても、利益を得るにはニーズがあることが大前提。まずはその地域にどのようなニーズがありそうかをリサーチし、借り手がつきそう、買い手がつきそうといった判断で、賃貸か売却かを決定するのも一手です。